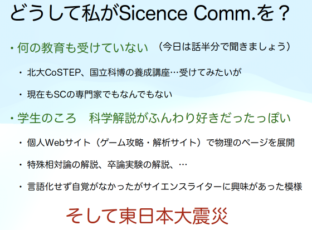駄文
山形大学理学部の理学共通科目「サイエンスコミュニケーターB」を2022年度から担当しています。専門的な教育も受けたことがないので正直無茶振りだと思いましたが、自分なりに考えは持っていたので、学生さんと一緒に自分も学ぶ機会にしてしまおうという算段で受け持つことにしました。
サイエンスコミュニケーションは広範な概念を包括する言葉です。研究者が市民に知識や成果を伝達するのもその典型ですし、楽しいイベントを開催して子どもたちに科学の楽しさを知ってもらうというのも一例です。しかしそれだけではありません。科学的な情報を踏まえた上で社会的に合意を形成するプロセスもサイエンスコミュニケーションですし、科学研究の主体が市民にあるシチズン・サイエンスの成果などを発信したり研究者を巻き込んでいく活動にもサイエンスコミュニケーションがあります。
授業では、こういった広汎なサイエンスコミュニケーションを俯瞰できる視点を養成することを目標としました。サイエンスコミュニケーションは楽しくキラキラしたイメージが持たれがちで、それは一面としては正しく大事な側面でもありますが、もっともっと広い視野で考えて将来の活動の土台になってほしいと思っています。
そのために、授業は以下の3つのパートで構成しています。
1. 知識を深めて議論する「ゼミパート」
サイエンスコミュニケーションの歴史や取り巻く様々な概念や理念を学習し、班ごとの調べ学習を行います。そしてプレゼンテーションとディスカッションを行っています。特に重視しているのは質疑応答のディスカッションで、必要に応じてコメントや解説を加えます。研究室配属後の研究発表などにもつながると思います。
2. リアルを知る「ゲストパート」
実際に何らかのサイエンスコミュニケーション活動をされているゲストをお呼びして、その活動内容や理念等のお話を交えながら実習を展開してもらっています。私も受講生と同じ立場で参加して学んでいます。またサイエンスライター小谷太郎さんによる集中講義も別途開催しています。
3. 自分で考えて手を動かす「実践パート」
半期の仕上げとして、企画・行動する活動です。実際に何かをやろうとしてみると、入念な企画や設計、調査と準備が必要であることが分かります。そのような経験を積むことを目的として、年度によって異なる活動を行っています。
これらの実習を通じて、学生さんには「質問力」を養ってもらうことを狙っています。ここで言う「質問力」が養われるということの意味は、
- 質問や議論ができるように慣れること
- 議論を通じて他者の考えに触れて、自分や他者の思考や理解が深まることを実感すること
- 次に自分が質問をする原動力にできること
などを含んでいます。科学に限らないコミュニケーションの一番大事なところであり、卒業研究・大学院やその後の人生できっと役に立つスキルになります。